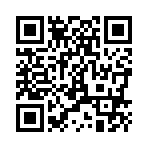甘利山
甘利山
7月定例山行
2023年7月23日
参加者14名 7月定例山行
2023年7月23日
■コース
島田中央公園第5駐車場(5:30)―藤枝岡部IC―〈新東名・中部横断道〉―道の駅なんぶ―白根IC―道の駅しらね―広河原駐車場(8:15)
広河原登山口(8:35)…甘利山(9:01〜08)…奥甘利山(9:40〜52)…御所山分岐(10:37〜47)…千頭星山(11:14〜44)…大西峰・奥甘利山コル(12:29〜35)…甘利山(13:04〜14)…広河原登山口(13:35)
累積標高差/647m 距離/7.85km 最高標高/2138m 最低標高/1641m 行動時間/約4時間(休憩含まず)
広河原駐車場(13:50)―道の駅しらね―白根IC―〈往路〉―島田中央公園第5駐車場(16:45)
■天候:曇り時々晴れ
■交通手段 レンタカー(ハイエース2台)
連日の連日の猛暑の中、涼を期待して企画された7月定例山行であった。甘利山は1640mの登山口まで車で上がることができ、夏の花々が咲く山頂まではわずか30分程で登れる。さらに千頭星山まで足を延ばしても、笹の中の穏やかな縦走路で、比較的容易に2千メートル峰に達することができるのが魅力だ。
レンゲツツジのシーズンには満杯となる駐車場だが今日はまばらで、暑さのためかハイカーは少ない。こちらの参加者も当初より減って14名となったが、皆さん体調も万全に夏の山に臨まれているようだ。
今日は定例山行初参加となる新会員への研修も兼ねて、ゆっくり丁寧に花を楽しみながら歩くことを心掛けた。ツツジ苑(売店)脇の登山口から鹿食害防止に張り巡らされた鹿柵ネットの中には、アザミ、ハクサンフウロ、ウツボグサなど夏の花々が早速に現われる。鹿の食害によって甘利山の花も少なくなったと聞いていたから、正直ホッとした。ところで有名なレンゲツツジの群落が食害防止ネットに守られていないのは、ツツジ類は鹿が食べないからとのことで、やや皮肉なことにも思える。同様の理由でこの山ではマルバダケブキの花も目立つ。
花々の名前を確認しながら木道を緩やかに上がっていくと、ひと登りで1731m甘利山山頂に着いた。登山口から少しガスの掛かった状態で、残念ながら富士山や甲府盆地の展望は得られない。
ここからは笹原の中の歩きやすい道となって千頭星山を目指す。風がなく時折ガスが引いて陽射しがあるとさすがに暑く、大量の汗をかく。奥甘利山(1843m)さらに大西峰(2066m山頂は通らず)への350メートルほどの登りは、無理をせずいつもより短いピッチで切って、疲労しないように心掛けた。時々の涼風が励ましとなって、また道の傍には相変らずシモツケ、ノイバラ、クガイソウ、カワラナデシコ、コオニユリなどの花々が咲き、歩きを飽きさせない。
奥甘利山周辺ではマルバダケブキが群落を成している。大西峰からは標高2千メートルを超え、笹と疎林の高原状の緩やかな尾根がガスに覆われて、幻想的な雰囲気を醸し出している。最後40m程を登り切るとモミ、カラマツの針葉樹に囲まれた2139m二等三角点の千頭星山(せんとうぼしやま)に到着した。山頂の木陰でのランチタイムは、20℃を下回る天然クーラーの中で涼を満喫できた。
往路はガスも上がり始め、戻った甘利山山頂からは今踏んできた千頭星山をはじめ、霞んではいるものの芦安の谷を挟んだ櫛形山や高谷山、甲府盆地の奥に茅ヶ岳、太刀岡山などを望めたが、富士山、鳳凰三山は最後まで顔を出すことは無かった。
甘利山への定例山行は2012年8月以来となる。この時はSHC登山教室を始めた年で、教室を経て入会された5名の新会員が参加していた。コロナ禍の2020年以降、登山教室は休止されているが、今回の山行には2名の新会員が参加し、久しぶりにフレッシュな雰囲気に満ちていた。また、今回はレンタカーを利用という新しい試み、運転を担われた3名の方に感謝申し上げたい。
出発地点・駐車場
山野草の中を甘利山へ出発
甘利山頂上周辺の山野草保護地域
甘利山頂上にて
サルオガセ
奥甘利山頂上にて
千頭星山への急坂1
千頭星山への急坂2
千頭星山への登り①班
千頭星山への登り②班
千頭星山頂上にて

コース・文 TANさん 写真SHIさん 投稿【SHC広報K】