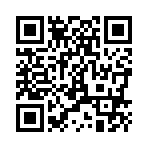十二ヶ岳
十二ヶ岳
2024年6月17日
2024年6月17日
参加者 2名
■コース
島田(6:00)=西浜中・小横毛無山登山口P(8:35-8:45)…文化洞登山口(8:55)…旧トンネル上峠(9:05)…ミネ山(10:04-10:10)…毛無山(10:53-11:05)…六ケ岳(11:40-12:00)…十二ケ岳(13:25-13:42)…桑留尾登山口(15:08-15:22)=(バス)=毛無山登山口(15:30)…毛無山登山口P(15)40-15:50)=島田(18:30)
毛無山登山口Pから歩いて文化洞登山口に戻り、毛無山を目指す。登山道はエゾハルゼミの賑やかな鳴き声の中、緩急を繰り返して登って行く。途中のミネ山の三角点にタッチすると横に手作りの小さな山頂標識が落ちていた。毛無山からは正面に大きな富士山がスッキリと見えている。咲いていた一輪のアヤメが印象的だった。ここからは時折ある岩場と細かなアップダウンで十一ケ岳に着く。鎖で岩場を降り、アルミ製の細い吊り橋を渡って十二ケ岳の結構な斜度を鎖とロープで登り返すが、150m程の登りがまだあるのと思えてくる。その途中で白い小さな花が咲いていた。ようやく十二ケ岳に着き二基の祠に手を合わせた。
休憩後桑留尾へ下るが以前来た時よりも道が悪くなっており慎重に下った。緩やかになったところで4人パーティーを抜いたがヘルメット着用、ハーネスも付けて、ガイド引率のパーティーのようだ。随分慎重な人たちだ。桑留尾からはバスで駐車地に戻り、帰途に着いた。(OSH)
本日のBGMは春ゼミの鳴く声、そしてすれ違う人も皆無で贅沢な貸切状態の山行でした。
立派な山名板が立つ毛無山山頂は、標高1500mのキリのいい数字と同様、対面の富士山もキリっとしてました。
次に目指した十二ヶ岳は一ヶ岳、二ヶ岳と順に表示板が現れ、途中展望地では西湖を抱えた富士山、河口湖と湖畔の街並など眺望もあって退屈しない。また十~十二までは鎖やロープ、金属製の吊橋、岩場で緊張感もありナカナカ…だった。今日は変化に富んだ登山道、かつ刻々変化する富士山、西湖、河口湖を時折眺めながらの歩きとなった。梅雨入り前の曇り空の下、優しく吹く風に癒されもした一日でした。(MAS)
登山者用が用意されていた

毛無山山頂

一ケ岳

富士山と西湖

十一ケ岳

十一から一度下ります

金属製吊橋

○○○ラン

二つの祠と富士山

最後の展望


コース(OSHさん)文(OSHさん、MASさん) 写真・ログ(MASさん) 投稿【SHC広報K】
2024年06月20日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 02:30 │Comments(0) │グループ山行
新倉山・霜山(山梨県富士吉田)
新倉山・霜山(山梨県富士吉田)
2024年6月13日
参加者 7名
■コース
島田中央公園(6:05)=新倉富士浅間神社P(8:22-8:38)…ゴンゴン石(9:40-9:50)…御殿(10:15-25)…大棚の滝分岐(10:43)…稜線分岐(11:17)…霜山(11:18)…稜線分岐(11:20-12:00)…大棚の滝分岐(12:25-12:30)…新倉富士浅間神社P(13:33-13:45)=日帰り温浴施設で一浴=道の駅「富士吉田」=島田中央公園(17:40)
新倉山中腹のアヤメ群生地を訪ねたいと今回のひらめは新倉山から霜山とした。登山口の浅間神社は外国の人たちに人気の場所。特に桜の時期はとても!ということでこの時期ならと思っていたが…なかなかの人でした。でもP代無料は有り難い。木花咲耶姫に因んだ398段の階段を上がると展望台で富士山が迎えてくれた。階段を上がるとアヤメ群生地だが、鹿に食べられ、また管理していた方の都合で咲いていたのは僅か、残念でした。少し上のゴンゴン石に着くころに地元の毎日組の方たちと会い、色々な花の咲くところを教えて頂いた。ゴンゴン石の直ぐ上が新倉山だが通過点のピークで写真も撮らずにスルーし、御殿に着いた。ここには正面に富士山が迎えてくれるデッキがあり、風も気持ちよく暫し休憩。先の地元の人たちに見える山を教えて頂いた。この先鞍部までは急なところもあり、大棚の滝分岐に着く。暫くは緩やかだったが三つ峠山からの府戸尾根に向かっての急坂となり、ロープが張られた箇所が多くなる。稜線に出、すぐ先の霜山の三角点にタッチ、稜線に出たところに戻り、正面に富士山を眺めながらの贅沢なランチタイムとした。
大棚の滝分岐まで戻る道は稜線からいきなりのロープ、注意を払って大棚の滝分岐まで戻ったが、少し手前で下りに使う斜面側でガサツと音が!鈴を鳴らし、口笛を吹いたりして分岐に戻り、大棚の滝を目指す。こちらも途中から結構急なところもあり、大棚の滝分岐に着くが何と道が悪いため立ち入り禁止となっていた。その先も急なところもあり、堰堤を過ぎると直に林道に出、浅間神社の駐車場に戻った。が、ここでも私にとってはカルチャーショック?直ぐの道は工事中で回れという。だが、外国の方は何でいけないんだと。結果そのまま駐車場に戻れた。押しは必要かもしれない!!と思った一幕だった。 今回は久々にロープ箇所が多く、少しの緊張もあり楽しめた歩きでした。
新倉山浅間公園駐車場からスタート

サクヤ(398段)階段が最初の試練

世界で有名、絶景スポットの新倉山展望台

アヤメ群生地は、鹿の害なのか残念な状況でした

穴に頭を入れて聴きました、ゴンゴン石

地元の方から解りにくい場所のキンランを見せていただきました

わずかでしたが、サンショウバラも見つけられました

御殿から見える富士と富士吉田の街は壮観でした

最終目的地は霜山です

秀麗な富士に見惚れながら、寡黙なランチでした

山梨の富士は、広い裾野を抱えた、形の良い、グレイトな富士でした

霜山からの下山は、ロープ頼りの急斜面の道です


ルート・文(OSHさん) 写真・ログ(SUZさん)提供 投稿【SHC広報K】
2024年06月15日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 01:38 │Comments(0) │グループ山行
中ノ尾根山
中ノ尾根山(浜松市の最高峰)
2024年6月7日
参加者 1名
■コース
6/6 兵越峠の駐車場で前泊
6/7 兵越峠(3:55)…水梨山(4:20)…朝日山(6:10)…平森山(7:10)…白倉山(7:50)…笠松山(8:10)…三又山(9:15~20)…ドーム(9:25)…中ノ尾根山(9:50)…ドーム(10:15~25)…三又山(10:30)…笠松山(11:15)…白倉山(11:45)…平森山(12:15~20)…朝日山(13:15)…水梨山(14:25~30)…兵越峠(14:45)
国盗り綱引き合戦で有名な兵越峠で一夜を明かした。電灯もないトイレがあるだけの駐車場だが、広く誰も居ない快適な車中泊を過ごせた。
登山口1150mから目的地の中ノ尾根山2270mを目指す。なだらかに標高を上げ、気づけば2000mを超える、長く緩やかな道のりだった。朝日山の東は、倒木が多く苔むした木々と立ち枯れの情景は、まさに深南部。平森山~白倉山の笹エリアは、獣道が錯綜し正解な道があるのか不明。方角だけ定め、ズンズン進む。しっとり濡れた笹で膝下はぐっしょりとなり、足元が重い。ドームへ辿り着くころには、ガスに覆われ眺望はなく少し残念だった。どこからでも登れそうな笹原を見上げ、ようやく中ノ尾根山に辿り着いた。広い山頂で、いくらでもテントが張れそう。
やや予定より山行時間が長くかかり急ぎ足で歩いたせいか、折り返し時点でバテ気味となった。糖分補給で身体を誤魔化し、戻った先で何を食べるかを楽しみに、長い下山路を歩き切った。
今シーズン初の銀竜草

朝日山の山頂

苔むした深南部

左から三又山、ドーム、中ノ尾根山
笹エリアの白倉山

イワカガミロード

新しい標識

三又山から望むドーム

ラストの中ノ尾根山

平坦な山頂

お洒落な火の用心

奥が朝日山

駐車場のオブジェ


ルート・文・写真・ログ ASAさん提供 投稿【SHC広報K】
2024年06月12日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 01:17 │Comments(0) │グループ山行
赤城山
赤城山
2024年6月1~2日
参加者 8名
■コース
6/1(土)
島田(5:40)=黒檜山北登山口P(11:05-11:20)…黒檜山(13:10-13:35)…駒ケ岳(14:22-14:30)…大洞登山口(15:10)…黒檜山北登山口P(15:25-15:32)=新坂=宿(16:05)
6/2(日)
宿(8:00)=観光(群馬県立歴史博物館・臨江閣・道の駅=島田(17:50)
島田の天気は今一だったが群馬に近づく程良くなってきた。まずは赤城神社にご挨拶をしてから歩き出す。いきなりの急登に足が重くなる。初心者の団体の後になったがゆっくり歩けていい。足を置くところから説明し、随分丁寧だなと思って聞いていた。所々でミツバツツジ、ヤマツツジが色を添えており、周辺の旅景色も見られる。急登を終えると直ぐに山頂に着いた。が、先の団体が腰を下ろしているので先の展望地で遅い昼食とした。霞んではいるが谷川方面が見え、眼下には沼田の町が見下ろせる。ここから駒ケ岳の先まではツツジの他ズミが多く、目を楽しませてくれた。階段が多い道を大洞に下り駐車地に戻ったが、時間が早いので新坂平のレンゲツツジを見に来た道を車で戻る。周辺はレンゲツツジ、ヤマツツジ、ズミが多く咲き競いきれいだ。羊も草を食み和ませてくれた。
二日目は天気が悪いので観光に切り替えた。山を下り、高崎の県立歴史博物館の国宝の埴輪などを観、前橋の臨江閣、最後は道の駅で買い物を楽しんで帰路に着いたが、高速道路では激しい雨。それでも島田に戻れば晴れで、終わりよければの山旅だった。(OSH)
今回の黒檜山は、百名山の中では難易度が低いようですが、登り始めから岩場の急登でついていくのに必死でした。
それでもレンゲツツジやシロヤシオに励まされ、ガスの合間から赤城神社をのぞむ景色に山の楽しさをしみじみ味わう山行でした。
2日目は雨となり、歴史博物館と臨江閣見学となり、今までご縁のなかった群馬にぐっと近づいた旅となりました。
帰りの道中はほぼ雨、時折豪雨でしたが、事故渋滞もクリアして、予定時間に無事、島田駅到着。
いつもながらの神技ですね。ありがとうございました。(TSU)
Day1 赤城神社駐車場から駒ケ岳方面を望む

辿り着いた大沼湖畔の対岸には青空が

黒檜山登山口駐車場から出発です

大沼と赤城神社を眺めながらの登山道

多くの登山者でひしめき合う急登の山道

山道には登山者を励ますシロヤシオたちが

ガスに包まれた黒檜山山頂に到着

あら不思議、黒檜展望地からは遠望の山が

ランチ後は足取り軽く駒ケ岳へ

道沿いには鹿の姿も

駒ケ岳山頂からは、大沼の全景が


初夏の花 純白の「ズミ」

下山後、新坂平の白樺牧場に訪れました

Day2 レンゲツツジに囲まれるはずのお弁当は、公園のベンチです

利根川を臨む「臨江閣」は、明治の近代木造建築


コース(OSHさん) 文(OSH・TSUさん) 写真・ログ(SUZさん) 投稿【SHC広報K】